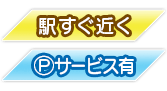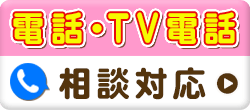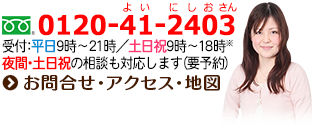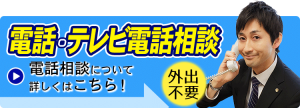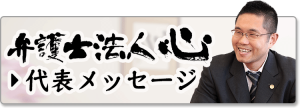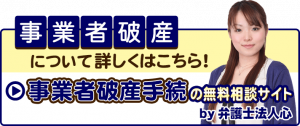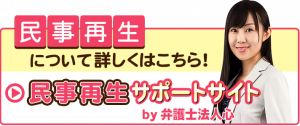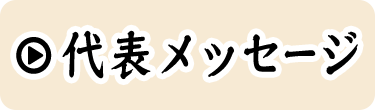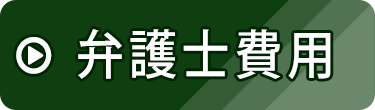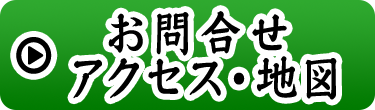法人破産のメリットとデメリットを解説
日本では、毎日のように大小様々な企業が倒産していますが、その多くはニュースにすらなりません。
いわゆる「倒産」にはいくつかのパターンがありますが、もっとも典型的な倒産は「法人破産」です。
「倒産=法人の破産」と思っている方もいるかもしれませんが、これは厳密には異なります。
では、法人破産は一体どのような手続きで、行うことによるメリット・デメリットにはどんなものがあるのでしょうか?
1 法人破産とは?
法人破産は「清算型」に分類される、倒産の一種です。裁判所に申立てをして行う、法的手続きの一種でもあります。
倒産には、他にも「再建型」というタイプもあります。債務総額を減らすなどして会社を存続させ、再建を目指す方法です。
これに対して法人破産は、会社の再建を目指すものではありません。会社の財産を処分して借金を清算し、借金問題を解決します。
そして、手続きが終わった後は、その会社の法人格は消滅してしまいます。
「会社を存続させられるのなら、再建型を選びたい」と思う方も多いと思います。
しかし、現実問題として、再建型の倒産をするのはハードルが高いです。再建の見込みがあることはもちろんですが、それ以外にも様々な条件をクリアしなければなりません。
もし再建の見込みが少なく、営業を続けていても借金が増えていくような状態の会社であれば、一般的には法人破産がおすすめです。
法人破産は、法人の消滅とともに借金経営を終わらせて、従業員や経営者の方が新しいステップに踏み出すための手続きなのです。
2 法人破産のメリット
「破産」という言葉にマイナスのイメージを持つ方も多いと思います。
確かに「自分の会社が破産する」と考えた場合、プラスのイメージを持つことは難しいでしょう。
しかし、法人破産にもメリットがあります。そのメリットを受けるために法人破産を選ぶ人も大勢います。
⑴ 債務がなくなり、借金の悩みを解決できる
経営難に陥っている法人の代表者の多くは、日々の資金繰りに悩んでいるはずです。
「事業を始めるときに借り入れたお金が返せない」
「今月請求が来る買掛金が支払えない」
「もう何ヶ月も家賃を滞納しているけれど、収入がなくて払える見込みがない」
このような悩みも、法人破産により解決します。
多額の借金を抱えていたとしても、法人破産をすればそれらの支払義務がなくなります。
債権者からの督促に怯える日々から抜け出すことができるのです。
⑵ 税金を含めた全ての債務がなくなる
個人が破産した場合、滞納している税金や養育費などといった一部の特殊な債務については、支払義務が継続します。こういった債務を「非免責債務」と言います。
しかし、法人が破産した場合、たとえ税金であっても支払義務が消滅します。
「全ての債務」が消えて無くなるところが、個人の破産とは大きく違う点です。
⑶ 代表者は再スタートを切ることができる
法人破産した会社の代表者は、ビジネス的に再起不能になると思われがちです。
しかしそういった制限は、少なくとも法律的には存在しません。
過去に法人を破産させた人でも会社を作ることができますし、取締役に就任することもできます(数年間は借入ができないなどの事実上の制約は存在します)。
3 法人破産のデメリット
法人破産には、当然デメリットもあります。
ここからは負の側面であるデメリットについて見ていきましょう。
⑴ 法人の財産は全てなくなり、法人が消滅する
個人の破産では、破産してもある程度の財産は破産者の手元に残されます。破産した人が消滅するわけではないので、生活に必要なものは手元に残せるのです。
しかし法人破産では、すべての財産が裁判所によって処分されてしまいます。
法人破産後は法人が消滅し、存続することはありません。法人の存続に必要な財産を残す必要がないので、全ての財産が失われてしまいます。
法人名義の自動車は売られてしまい、法人名義で保有している不動産なども失ってしまいます。普段からそれらの自動車や不動産を使っている場合は、法人破産後に不便を強いられてしまうでしょう。
なお、処分された財産は売却を経てお金に換えられますが、法人代表者などがそのお金を受け取ることはありません。全て債権者への弁済に使われます。
⑵ 従業員や取引先に少なからず迷惑がかかる
法人破産によって法人は消滅するため、法人に勤めていた従業員は全員解雇せざるを得なくなります。従業員に迷惑がかかるのは避けられないでしょう。
当然ながら、取引先にも迷惑がかかります。
まず、買掛金などの債務を払えなくなります。取引先はあてにしていた入金がなくなるため、資金繰りに困ってしまうでしょう。
また、既に請けていた仕事も破産によって続けられなくなってしまいます。約束していた品物の納品や、労務の提供などもできなくなるでしょう。
【一部の取引先にのみ借金を返すことはできない】
なお、迷惑をかけたくないと考えて特定の取引先にだけ支払いをした場合は、破産法で禁止されている「偏頗(へんぱ)弁済」に抵触するおそれがあります。偏頗弁済とは「えこひいき」になるような弁済です。
破産手続では全ての債権者を平等に扱う必要があるため、債務者が勝手に特定の債権者にのみ弁済することを禁じています。もし偏頗弁済を行うと、最悪の場合は法人破産の手続きが取り止めになってしまいます。
⑶ 代表者の自己破産も発生する可能性が高い
中小規模の会社の場合、法人の代表者が法人とほぼ一体化しているケースがよく見られます。例えば、法人の代表者が、法人の債務を連帯保証しているような場合です。
そういった場合、法人が消滅すると、法人の債権者はもはや法人に請求できないため、連帯保証人である法人代表者に支払いを請求することになります。法人の支払義務が消えても、連帯保証人の支払義務は残っているからです。
連帯保証人である法人代表者に満足な資力がなければ、法人代表者も連鎖的に自己破産することになります。実際にそういった事例も多いです。
代表者個人が自己破産すると、代表者の自宅や高価な車などが裁判所によって処分されてしまいます。
また、税金の支払義務は、個人の場合は免除されることがないので注意が必要です。
4 倒産・破産のご相談は弁護士へ
多くの法人代表者は、倒産の際に法人の債務を清算して法人を消滅させる法人破産を選択します。
しかし法人破産にもメリットとデメリットがあるため、実行前に慎重に検討しなければなりません。
倒産案件に慣れた弁護士であれば、どのタイプの倒産を選ぶべきか、その際の注意点は何かなどを、冷静かつ客観的に判断して、ご依頼者様にお伝えることができます。
弁護士法人心には、倒産・破産案件に熟練した弁護士が揃っています。法人の経営が苦しくなった方は、どうぞお早めにご相談ください。